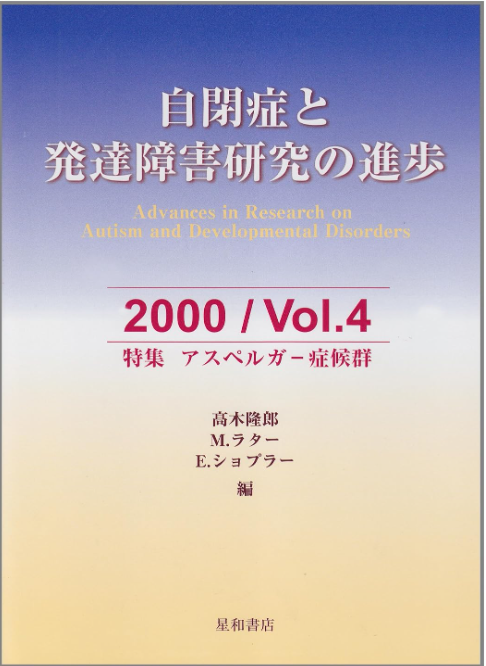
『自閉症と発達障害研究の進歩』2000/Vol.4(星和書店)に、1944年にハンス・アスペルガーがウィーン大学医学部に提出した論文の日本語訳版が載っていたので、じっくりと読んでみました。
1944年というと、時代は第2次世界大戦中です。しかも、ウィーンはナチスの支配下にあり、こうした障害のある子ども達についての治療教育について、実践した上で論文発表するということが可能だったというだけで尊敬に値する業績だと思いました。
ハンス・アスペルガーが記述した事例が、実に印象的です。「きわめて重度の社会適応の障害を示す、ことに高度の変わり者的児童」と紹介されているフリッツ、Vなる児童の様子は、今日、日本の多くの場所にいる子ども達の様子と重複しているのです。例えば、「言いつけに従わず、したいことをしたり、言われたことの正反対のことをする」、「幼い時から落ち着きがなく、どこにでも行き、何でも手に取りたがり、すべてに気をひかれ、抑えようとすることは一切無視した」。「破壊欲求が著しく、手にしたものをたちまち引き裂いたり、壊したりした」という。また、「仲間が彼をちょっと刺激すると、彼はますます攻撃的になり、手に届くものを何でもとって、すぐさま叩いた(一度はハンマーで)」。また、「(こうした)子どもに特徴的なことは力強い命令や禁止、怒りや優しい話しかけや甘やかしに、従順や順応で反応せず、反対に拒絶や悪意、攻撃で向かってくることである。」「普通児では先生の怒り、脅しなどの感情が結局はわがままや反抗をおさえて、正しい服従をもたらすのであるが、われわれの自閉児たちでは正反対である。すなわち先生の感情を、彼らは敵意ある目を輝かせて見つめ、怒らせて喜んでいる。」これ以外にも、実に詳細に彼らの様子を記述しているのですが、これ以上は省略します。
そして、何と言っても素晴らしいのは、こうした彼らへの教育的な接し方や教え方に関する内容です。
「第1に、教育的手段は一切感情的にならずに行われなければならない。教育者はけっして怒ったり、不機嫌になってはいけないが、また好かれようとか子ども向きになろうとしてはいけない。」「教育者は心から平静で、しっかりと落ち着いていなければならない。」「彼らは社会適応も知能を媒介しなくてはならず、一切を理解によって学ばなくてはならない。」「些細な日常的仕事も学校の課目のように勉強し、体系的に整理しなければならない。」「こうした子ども達の多くは、正確な時間表を作る、すなわち起床からはじめて、1日の仕事と義務を整理しておくのが良い。」
ウィーン大学小児科所属の治療教育部で、200例を超える「自閉症児」との療育実践があったからこそ導き出された内容だと思います。そしてこれは、現在でも通じる自閉症児教育の基礎だと感じました。
「(彼らは)発達も適応も可能な人格であり、発達の過程で以前には思いもしなかった社会適応の可能性が浮かびうることが示されたと思う。これらの事実はこれらの困難な問題をかかえた人々に対するわれわれの見地、われわれの価値判断を決定させ、彼らにわれわれの全人格でもって立ち向かう権利と義務があることを確認させ、愛情に満ちた教育者が身をもって打ちこんでこそ効果が引き出せることを確信させるものである。」という結論ともいえる文章は、自閉症児教育は難しいが、その醍醐味は計り知れないという私の持論とオーバーラップするものでした。この論文を読んで、私はハンス・アスペルガーの大ファンになってしまいました。
ちなみに、このハンス・アスペルガーの論文を再評価したイギリスの自閉症研究者ローナ・ウィングの1981年の論文もこの本には掲載されています。





