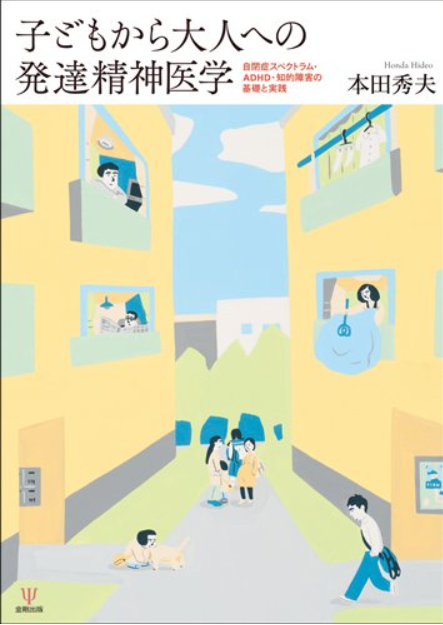
本田秀夫先生の本なのに、見落としていたため今回初めて読みました。内容的には、医師や教師など専門職向けの内容でした。10年以上前に出版された本なので、「アスペルガー症候群」や「広汎性発達障害」など、今はもう使われていない診断名が使用されていますが、内容は全く古びていません。
「障害」が「社会」との関連の中で顕在化するという指摘も鋭く、中でも「軽度精神遅滞」や「境界知能」の人たちにとって、現代は受難の時代であるという指摘は、実に頷かされる内容でした。彼らに対する「適切な支援に向けた課題」として、①早期発見と早期介入、②境界知能の人たちへの教育と福祉制度の整備、③精神科医の関与による学校精神保健の充実の三つを挙げています。特に①では、早期発見と早期介入によって、彼らの社会適応を促進することは可能だけれども、早期から集中的に訓練すれば追いつくといった期待を専門家が助長するような対応は厳に慎むべきであるという指摘は、私自身も常に心がけていることでしたので、納得できました。
この本の中で、最もお薦めしたいのは第17章の「知的障害のための環境作りー「ユニバーサルデザイン」から「コンプリヘンシブ・デザイン」へー」です。ユニバーサルデザインは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの身体障害者を想定して考えられたものなので、知的障害者や自閉症者のための環境づくりとしては不十分な部分があり、「構造化」という基本戦略が必要なことを説明しています。実はこの構造化こそ、私が幼稚園や保育園の先生方に導入を強く勧めているものなのです。スケジュールの提示等の視覚支援、注意が引きつけられてしまう玩具やスイッチ等を見えなくする視覚遮断などが含まれます。どんな人にも分かりやすく使い勝手のよい環境に整えることと、不適応行動を予防し適切な行動を促す環境にすることを両立させる理念として、筆者は「コンプリヘンシブ・デザイン」を提唱しています。ユニバーサルデザインという言葉以上に、このコンプリヘンシブ・デザインという理念が社会に浸透することを心から願っております。
追記:この本の出版元である金剛出版のホームページを覗いたら、この本が『新訂増補 子どもから大人への発達精神医学ー神経発達症の理解と支援-』として、今月末に出版される予定になっていました。興味のある方は、是非新しい方の本を読むことをお薦めします。診断名等を改訂し、内容も追加されているようです。私も読んでみたいと思います。





